|
レーザー光の吸収を利用して時計反応の機構を探る
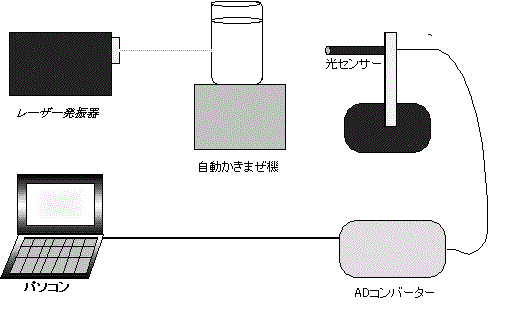 [目的]ヨウ素デンプン反応で深青色になった溶液が学校にあるヘリウム・ネオンレーザーの光をよく吸収することに気がついたので、透過光を光センサーでモニターすれば反応が進行する様子を詳しく調べられるのではないかと思った。ヨウ素デンプン反応について以上のことを実際に試してみた。 [目的]ヨウ素デンプン反応で深青色になった溶液が学校にあるヘリウム・ネオンレーザーの光をよく吸収することに気がついたので、透過光を光センサーでモニターすれば反応が進行する様子を詳しく調べられるのではないかと思った。ヨウ素デンプン反応について以上のことを実際に試してみた。
[原理]
でんぷん溶液にヨウ素溶液を加えると、でんぷん-ヨウ素複合体が形成され青色になる反応は、ヨウ素-でんぷん反応として知られている。
例として、でんぷんとヨウ化カリウムを溶かした溶液に、過酸化水素水を加えると、次
 の反応により青色になる。 の反応により青色になる。
H2O2+2I−+2H+→I2+2H2O (1)
I2+I−→I3− (2)
I3−+デンプン→I3−―デンプン (3)
(青色)
しかし、デンプン溶液にチオ硫酸ナトリウムを溶かしておくと次の反応によってI3-はつくられないので青色にならない。
2S2O32−+I2→2I−+S4O62− (4)
そしてチオ硫酸イオンが消費されて無くなると(2)と(3)が起こって青色になる。
よって、青色になるまでの時間(誘導期という)を測定すれば反応速度に関する知見が得られる。
〔実験1〕
〈溶液〉
1.溶液A:作り方
a. 沸騰水100mlに可溶性デンプンを0.2gをいれ、よくかき混ぜる。
そして、沸騰させないように3-4分加熱し、800mlにうすめる。
b.濃酢酸(CH3COOH)を30ml加える。
c.酢酸ナトリウム(NaOCOCH3)を4.1g加える。
d.ヨウ化ナトリウム(KI)を50.0g加える。
e.チオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)を4.7g加える。
f.溶液を冷やし、1.0リットルにうすめる。
2.溶液B:次の各濃度の過酸化水素水を用意する。
(B1)3.0% (B2)2.4% (B3)1.8% (B4)1.2% (B5)0.6% (B6)0.3%
〈手順〉
 1.300mlビ−カ−に溶液Aを100mlいれる。 1.300mlビ−カ−に溶液Aを100mlいれる。
2.300mlビ−カ−に溶液Bを100mlいれる。
3.二つの溶液をよく混ぜる。
4.ネオン・ヘリウムレ−ザ−光線を溶液に当てて、透過した光の強度を0.02秒ごとに光センサ−でモニタ−し、パソコンに取り込む。
〔結果〕
光センサーでモニターした透過光強度の変化から溶液が青色になるまでの時間は表の通りであった。
〔実験2〕
〈溶液〉
1.溶液A:実験1と同じ。
2.溶液B:次の各濃度の過酸化水素水を用意する。
(B1)0.35% (B2)0.28% (B3)0.21% (B4)0.14% (B5)0.07% (B6)0.035%
〈手順〉実験1と同じ。
〔結果〕
光センサーでモニターした透過光強度の変化から溶液が青色になるまでの時間は表の通りであった。
表
実験1 実験2
溶液B 誘導時間(秒)液温(℃) 誘導時間(秒)液温(℃)
1 9.62 14.8 36.16 26.8
2 12.22 15.8 46.70 27.5
3 15.47 13.3 65.26 27.0
4 18.99 16.6 103.16 27.0
5 25.94 25.9 279.36 27.5
6 39.16 25.5 1020.00 27.0
〔考察〕
1.過酸化水素水の濃度が小さいと、誘導期は長くなることが分かった。
2.横軸に過酸化水素濃度またはその逆数,縦軸に誘導時間をとってデータをプロットすると誘導時間が初期過酸化水素濃度の逆数に比例している領域があり、この領域では時計反応の律速段階は、過酸化水素ともう一つの化学種の2分子反応であると考えられる。
3.液温の影響が考えられるので今後は液温をコントロールしながらの実験も必要である。
|